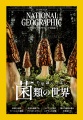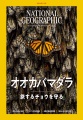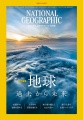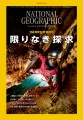第1回 長沼毅 謎の深海生物にさぐる宇宙生命の可能性(前編)
< 1 2 3 4
必ずやあります。けれど、それは見えていません。第2衛星エウロパにも火山があってしかるべきですが、それは見えない。なぜなら、表面が氷で覆われているからです。表面が氷で覆われた星なんて、変な星があるものだと思うかもしれませんけれど、太陽系を広く見わたすと十数個あると言われています。我が地球でさえも、過去に3回あるいはもっと多くの回数、全部凍った過去があるんです。そう考えれば、星が全部凍ってること自体は不思議でも何でもない。
大事なことは、その氷の底に必ずや火山があるということです。火山の熱のせいで氷の底が解けて、液体の水になって、その液体の水の層がこの星全体を取り巻いている。表面が氷、内側が岩石、その間にサンドイッチのように挟まれた水の層がある。これを内部海といいます。

木星には、特に大きい衛星が4つあります。今から400年ほど前にガリレオが発見したのでガリレオ衛星と呼ばれています。そのうちエウロパとガニメデには内部海があると考えられています。今、実は内部海を持っている星は、太陽系に14個あると想定されています。あくまで想定ですよ。エウロパはその筆頭です。
エウロパの内部海の海底に海底火山があるとして、地球の海底火山には何がいましたか。食べ物も太陽の光もいらず、海底火山さえあれば自分で栄養をつくってしまう謎の深海生物がいました。そうだとしたら当然のことながら、このエウロパにも謎の深海生物がいるかもしれないという話が出てきます。
高校生の私はその謎に惹かれ、大人になったらこの研究をしようと心に決めたんです。それで実際に大人になってJAMSTECというところに入ってですね、「しんかい2000」や「しんかい6500」といった潜水艇に乗って研究をしたわけです。
<後編につづきます>

長沼 毅(ながぬま たけし)
広島大学大学院生物圏科学研究科准教授。海洋科学技術センター(現JAMSTEC)研究員を経て、1994年より現職。深海や南極、砂漠など極限環境の生物を研究する。著書に 『死なないやつら』(講談社ブルーバックス)、 『地球外生命――われわれは孤独か』(岩波新書)、 『ここが一番面白い! 生命と宇宙の話』(青春出版社)など。
※ この連載は、2013年12月に相模原市立博物館で開催された講演会『宇宙にいのちを探す』の各講演を再編集したものです。

アストロバイオロジー特集が読める!
『 ナショナル ジオグラフィック2014年7月号』
7月号特集「宇宙生物学のいま」ではSETIの創始者フランク・ドレイクから、木星の衛星エウロパの生命探査計画まで、アストロバイオロジー(宇宙生物学)の最先端をご紹介。ほかにも「巨大魚イタヤラ」「中国 巨岩の帝国」など驚きの特集をたっぷり掲載しています。こちらからどうぞ!
< 1 2 3 4
「宇宙に生命を探せ!」最新記事
バックナンバー一覧へ- 第12回 高井研 私を氷衛星地球外生命探査に連れてって エンケラドゥスvsエウロパvsケレス(後編)
- 第11回 高井研 私を氷衛星地球外生命探査に連れてって エンケラドゥスvsエウロパvsケレス(前編)
- 第10回 鳴沢真也 正しい宇宙人の探し方~SETIの話(後編)
- 第9回 鳴沢真也 正しい宇宙人の探し方~SETIの話(前編)
- 第8回 田村元秀 太陽系外惑星と宇宙における生命(後編)
- 第7回 田村元秀 太陽系外惑星と宇宙における生命(前編)
- 第6回 山岸明彦 火星での生命探査計画(後編)
- 第5回 山岸明彦 火星での生命探査計画(前編)
- 第4回 堀川大樹 宇宙生物学とクマムシと私(後編)
- 第3回 堀川大樹 宇宙生物学とクマムシと私(前編)

 アルマ望遠鏡始動!
アルマ望遠鏡始動! 星を食らう ブラックホール
星を食らう ブラックホール 探査車が見た火星
探査車が見た火星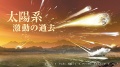 太陽系 激動の過去
太陽系 激動の過去 『三体』で注目の説、「宇宙人は互いを恐れて隠れているだけ」か
『三体』で注目の説、「宇宙人は互いを恐れて隠れているだけ」か 6月4~6日もオーロラが広く出現か、2024年は異例の当たり年に
6月4~6日もオーロラが広く出現か、2024年は異例の当たり年に NASAの次の有人月面探査車はどれになる? 3つの最終候補を解説
NASAの次の有人月面探査車はどれになる? 3つの最終候補を解説 【動画】80年に一度現れる新星がもうすぐ夜空に、かんむり座T星
【動画】80年に一度現れる新星がもうすぐ夜空に、かんむり座T星 ビジュアル 銀河大図鑑
ビジュアル 銀河大図鑑
 COSMOS コスモス いくつもの世界
COSMOS コスモス いくつもの世界
 宇宙48の謎 地球外生命体を探せ!
宇宙48の謎 地球外生命体を探せ!
 MARS マーズ 火星移住計画
MARS マーズ 火星移住計画
 クマムシ博士の クマムシへんてこ最強伝説
クマムシ博士の クマムシへんてこ最強伝説
 ビジュアル 大宇宙(上)
ビジュアル 大宇宙(上)
 ビジュアル 大宇宙(下)
ビジュアル 大宇宙(下)
 ナショナル ジオグラフィック日本版 2019年7月号
ナショナル ジオグラフィック日本版 2019年7月号